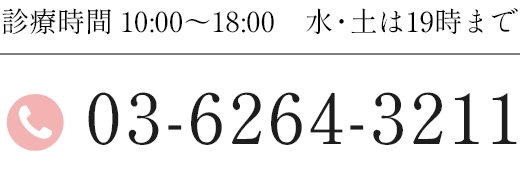歯に関するお悩みは
ささいなことでもご相談ください
当院では、むし歯や歯周病といった一般的な歯科治療に加え、根管治療や入れ歯の作成など、幅広い診療を行っております。また、お口の中だけでなく、ライフスタイルやどのような健康を望まれているかをうかがい、一人ひとりの患者さんに合わせた診療方針をご提案し、お口の健康と全身の健康をサポートさせていただきます。不安やお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

当院の歯科治療のこだわり
Commitment
丁寧な
カウンセリング
患者さま一人ひとりのご要望や不安に真摯に向き合い、わかりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。治療内容やご不明な点について、何でもお気軽にご相談ください。患者さまが納得のいく治療計画を一緒に立てていきましょう。
清潔で落ち着いた
診療環境
患者さまがリラックスして治療を受けられるよう、清潔で落ち着いた診療環境を整えております。最新の医療機器を導入し、常に衛生管理を徹底しております。
痛みに配慮した
治療
治療時の痛みを最小限に抑えるため、様々な工夫を凝らしています。麻酔液の種類や注射方法など、患者さまに合った方法をご提案いたします。また、治療中の痛みにも配慮し、随時声をかけながら治療を進めていきます。
何かありましたらすぐ教えてください。
一般歯科の主な疾患と治療
むし歯
虫歯は、細菌によって歯が溶けてしまう病気です。初期の虫歯であれば、痛みを感じないこともありますが、歯磨きを怠ったり治療しないまま放置すると、だんだん悪化してやがて痛みを伴うようになります。むし歯は早期発見・早期治療が肝心で、初期であれば簡単な対処で済む場合がほとんどです。痛みが無くても定期的に歯医者に受診し、口内を健康に保てるよう心がけましょう。
むし歯の予防について

ブラッシング
むし歯を予防するためには、毎日の歯磨きが欠かせません。
歯ブラシを使う際は、歯と歯茎の境目や歯と歯の間を意識して磨き、歯垢をしっかり落としましょう。また、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスも併用することで、歯と歯の間の汚れもしっかりと取り除くことができます。

キシリトール
キシリトールは、虫歯菌が利用できない甘味料です。通常、虫歯菌は砂糖をエサにして酸を作り、歯を溶かしますが、キシリトールは虫歯菌のエサにならないため、虫歯菌の活動を抑制することができます。また、キシリトールは唾液の分泌を促し、口の中を洗い流す効果もあります。ガムやタブレットなど、さまざまな製品に配合されており、手軽に摂取することができます。

フッ素(フッ素化物)
フッ素は、歯の表面を強化し、酸に対する抵抗力を高める働きがあります。歯の表面にフッ素が取り込まれると、歯のエナメル質が再石灰化し、より丈夫になります。また、虫歯菌が作り出す酸を中和する効果もあります。当院では定期検診の際に高濃度のフッ素塗布を行います。また、歯磨き粉や洗口液などにもフッ素は含まれています。
歯周病
歯周病は、歯を支える歯茎骨などの歯周組織や炎症が起こる病気です。初期段階の「歯肉炎」では、歯茎が赤く腫れたり、ブラッシングするときに出血がありますが、痛みを感じない場合が多いため症状に気づきにくく、知らない間に進行することがあります。定期的な歯科検診を受けることで歯周病の早期発見につなげることがとても大切です。
根管治療
歯の根の内部には、神経や血管などが通っている「歯髄(しずい)」という組織が存在します。根管治療とは、この歯髄が炎症や感染を起こしたときに行われる治療です。歯髄の炎症や感染を放置すると、歯の痛みや歯肉が腫れたり、根の周囲に炎症が広がったりします。さらに悪化すると、リンパ節が腫れ、全身に影響を及ぼすこともあります。根管治療では、これらの症状の軽減や治療を行います。
入れ歯治療
入れ歯は、歯を失ってしまった部分に人工の歯を装着し、噛む機能や見た目を回復させるためのものです。大きく分けて、残っている歯にバネをかけて固定する部分入れ歯と、歯が全くないところに装着する総入れ歯があります。材質や構造によって様々な種類があり、保険が適用されるものと、自費診療になるものがあります。当院では患者様のご希望に合わせて最適な入れ歯をご提案致します。
一般歯科のよくある質問
むし歯治療のよくある質問
- どうして虫歯ができるんですか?
-
虫歯になる条件として歯質(歯)・細菌(虫歯菌)・時間・糖分(砂糖を含む食べ物)が挙げられます。
歯にプラーク(歯垢など)が付着し、そこには多くの細菌が存在します。細菌は糖分を分解して酸を作り出し、歯を溶かします。お口の中の環境pHが5.5以下になると脱灰を始めてしまいます。この酸性の状態を中和するためには唾液の作用が非常に大事になります。
唾液によって酸や糖分を洗い流してくれたり、アルカリ性物質を産生したり、酸を弱めてくれることによってお口の環境が中和して再石灰化します。しかしpHを元に戻すためには2〜3時間かかります。間食などが多いとお口の中が長時間酸性状態になり、歯がどんどん脱灰してしまいます。また睡眠時も唾液の量が減少しますので夜食や磨かないで寝てしまうと虫歯になりやすくなりますので注意してください。 - 歯が黒いと必ず虫歯ですか?
-
いいえ、歯が黒くなった時は必ずしも虫歯になった訳ではありません。歯に着色がついたなどの他の原因もございますのでぜひ一度ご来院ください。
- 歯の神経を取るとはなんですか?
-
歯には神経が通っていて生きています。
しかし虫歯が神経まで進行している場合、神経は細菌に侵され、痛みが出たり、膿がたまってしまったり様々な症状が出ます。そうなった場合、神経を残す事はできませんので、神経を取る治療というものが必要になります。虫歯が神経まで進行していない場合、痛みはほとんどありません。歯の神経まで虫歯が進行するとズキズキした痛み、何もしなくても痛む、夜中に激痛が走るなどの症状が診られます。歯の神経が全体的に感染してしまうと自然治癒することはありません。
神経の治療の流れは、まず虫歯の部分を削って完全に取りのぞきます。ファイルと呼ばれる細い針のようなもので感染した歯の神経を機械的に除去し、化学洗浄(根管洗浄)を行い、根管内をきれいにしていきます。
症状がなくなれば歯の神経の代わりになる防腐剤をつめて根管治療は終わりになります。 - 子供の虫歯予防にはどんな種類がありますか?
-
虫歯予防にはいくつか種類があります。
シーラント、フッ化物を歯面に塗布、フッ化物洗口、フッ化配合の歯磨き粉を使用する、仕上げ磨き等があります。シーラントとは、歯の溝にシーラント材と呼ばれる固定性のフッ素を入れて光で固めるものです。子供の生えたての歯は虫歯になりやすいため、シーラントを入れることで、歯に虫歯菌が入り込むのを防ぐことができます。 - フッ素はいつから使ったほうがよいですか?
-
生えたての歯は柔らかく、もろく虫歯になりやすいです。唾液に含まれているカルシウムにより経年的に強度を増していきます。乳歯だと生後6ヶ月、永久歯だと6歳ごろに歯が生えてくるのでフッ素をその時期に使用するのが良いと思います。
まずは下の前歯が生えたころから歯科医院に定期的に通って塗ってもらうようにしてください。しかしブラッシングの習慣やきちんとした食生活をすることが何よりも大切です。 - 初期虫歯って何?
-
歯の表面が白色や茶色くなっている状態の事です。
初期虫歯の状態であれば歯を削る必要はないですが、今後虫歯が進行する可能性があるため
- フッ素を取り入れる
- 歯磨きを強化する
- フロスをしっかり行う
- 間食や砂糖を控える
- キシリトールガムを噛む
- 虫歯を放置するとどうなりますか?
-
虫歯は進行状況に応じて、C1~C4の4段階に分類されます。
(C1)初期の虫歯は痛みがありません
(C2)虫歯菌が歯の内側深く(象牙質)に進行すると、ズキズキ痛むようになります。
(C3)そのまま放置していると、激痛で夜も眠れないくらいの症状が出現します。
(C4)それを越えると歯の神経が死んでしまい、逆に痛みを感じなくなります。さらに放置すると歯の根まで虫歯が進行し、化膿して膿がたまります。ここまでくると、最悪の場合、抜歯になります。 - 詰め物をした後、しみる症状があります。なぜですか?
-
詰め物をする際に歯を削ります。削ったことによって神経が近くなり、冷たいものやかむときの刺激を感じやすくなります。個人差はありますが神経部分に第2象牙質(神経を守るため新しくつくられる象牙質)ができて歯質に厚みができて落ち着いてきます。
それでも痛みなど症状が続く場合は、神経まで虫歯菌が感染している可能性があるので神経の治療になる場合があります。 - 虫歯を放置して歯の頭(歯冠部)がない状態です。なるべく歯を残したいのですができますか?
-
状態により残せる場合もあります。
歯の頭:歯の根っこ = 1:1で保てる場合は被せものを作製できます。
しかし歯ぐきの中や深い虫歯の場合、保存が困難な場合もあります。 - 虫歯になったら痛みが出ますか?
-
痛みが必ず出るとは限りません。大きな虫歯でもまったく痛みが出ないことがあります。
また、痛みを一時的に我慢することで痛くなくなります。これは虫歯が歯の神経まで到達し神経が死ぬと痛みを感じなくなるためですがこのまま放置すると、治療ができないほど歯のダメージが大きくなります。 - 虫歯の治療期間が長いのはなんで?
-
虫歯の進行度により治療方法が異なり、小さい虫歯の場合は1日で終わります。
大きい虫歯の場合、詰め物(インレー)や土台、被せものが必要になります。虫歯が神経まで達してしまった場合、神経を取る根管治療を行います。根管内部の感染した神経や細菌をしっかり除去し、再発を防ぐために洗浄・消毒を繰り返さなければいけません。
その後、歯型取り、セット・調整という順で進めていきます。経過観察のために治療期間を開ける場合もあります。できるだけ神経を残すことを考え、今後の治療方針を判断していきます。また長時間口を開けておく、治療期間中の食事といった患者様の負担も考慮して治療を分けて行います。 - 詰め物がとれました。つけるだけの処置できますか?
-
はい、可能です。しかし詰め物が取れてしまう原因があります。
セメント(詰め物を歯と接着させる接着剤)の経年劣化、詰め物の下で虫歯ができてしまった、噛み合わせなど様々な要因がありますので検査をすることをお勧めします。 - 虫歯になりやすい人の特徴は?
-
- 歯をあまり磨かなかい
- 磨き方が不十分
- 甘い物をよく食べる
- 間食が多い
- 口で呼吸する
- 歯並びが悪いなど
- 虫歯になりやすいところはどこですか?
-
特に歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目、奥歯の咬み合わせの溝は虫歯リスクが高くなります。
そして、就寝中は唾液の量が少なく細菌が活発になる時間帯で虫歯になりやすいです。できるだけ夜の歯磨きは念入りに磨きましょう。
また、5才~6才にかけて生えてくる最初の永久歯である第1大臼歯(6才臼歯)は、乳歯列の一番奥に生え、見えにくく、完全に生えるまで時間(1年~1年半)もかかることから磨き残しが多くなりやすいところです。
定期的に小さなレントゲンを撮影して、虫歯のチェックをすると良いでしょう。 - プラスチックの詰め物をした所が茶色くなるのはなぜ?
-
プラスチックが劣化をするためです。お口の中は酸やアルカリ、温度差があったりと環境の変化が激しいのです。
また、プラスチックの容器にカレーなどを入れた時、色が残るのをイメージして頂くと分かりやすいのですが、普段の食生活でのコーヒー、紅茶、ワイン、カレーなど色素の濃いものを摂取される場合、徐々に変化がみられます。 - プラスチックの素材はとれやすかったり虫歯になりやすいといわれたが、なぜ?
-
詰め物は歯との接着していて、特に水分をシャットアウトする事がとても重要で少しでも水分が入ると取れやすくなってしまいます。唾液を完全にシャットアウトすることは難しいため取れやすいと説明をさせて頂いております。
また、プラスチック素材は光で固めて歯と接着します。その際、量に比例して収縮をします。その力が接着している歯質を引っ張り、微小なレベルでの亀裂が起こってしまいます。そういった小さな隙間に虫歯菌は入りこみます。歯ブラシなどは届かないので、だんだんと周りに虫歯が広がってしまうことがあります。
そのため奥歯の範囲の広い虫歯にはおすすめしておりません。 - 知覚過敏は虫歯とは違うの?
-
違います。
知覚過敏とは、冷たい物、甘い物、歯ブラシによって感じる痛みのことで、虫歯や歯の神経の炎症などがない場合にみられる症状です。歯の構造として、エナメル質という歯の表面の組織があり、その下に象牙質という組織があります。象牙質の中に神経があるため、通常、痛みや刺激は歯ぐきやエナメル質によって守られています。虫歯や食いしばりなどにより象牙質が露出してしまうと刺激は神経へ伝わり痛みを感じてしまいます。 - なぜ甘い物が虫歯になるのですか?
-
虫歯は歯が脱灰されることから始まります。その原因は酸を作り出す菌が歯に付着する事で起こります。その細菌の栄養源が糖類なのでその菌を繁殖させる要素になってしまうからです。
- 虫歯はどのように進行していきますか?
-
虫歯がエナメル質にとどまっている時に痛みはありません。象牙質に達すると刺激が神経まで伝わって暖かいものや冷たいものや甘いものに対して様々な反応が起きます。歯髄の炎症がひどくなると痛みもひどくなります。放置すれば歯髄は死に根の中が腐りさらに根の外の骨まで腐ってきます。
これらの変化は一見しただけでは判別は不可能です。外から見て何ともなくても歯髄がくさって根の外に膿がたまっていることもあります。 - 虫歯になるとどんな症状がおきますか?またその段階ごとの治療方法を教えてください。
-
- (CO)要観察歯
脱灰しかけている程度で症状が全く無い状態。局所フッ化物療法によって再石灰化を図る。 - (C1)エナメル質のみのう蝕
ほとんど自覚症状はなく溝が黒くなっている程度です。シーラントをつめる。 - (C2)象牙質まで達したう蝕で歯髄との間に一層の健全象牙質が存在するもの
自覚症状はほとんどないか水にしみる程度です。健康な歯質を最大限に残してむしばを治療する。 - (C3)歯髄まで達した象牙質う蝕
大きな穴があく場合が多く神経まで侵されている状態です。暖かいものがしみたり、何もしなくてもずきずきいたんだり、噛み合わせるときに痛んだりします。但し慢性化して痛まない場合もあります。
健康な歯質を最大限に残してむしばを治療する。必要に応じて歯の根の治療(根管治療、歯内療法)を行う。 - (C4)残根状態
根のみ残っている状態です。多くの場合抜歯となります。
- (CO)要観察歯
- 虫歯は自然に治りますか?
-
虫歯が自然に治ることはありません。小さな虫歯も放置すれば進行し、やがて神経まで達してしまい、神経や歯自体をとる等大掛かりな治療が必要になります。また、治療回数や費用面でも患者様の負担は増えていきます。異常に気付いたら、早めに歯科医院を受診しましょう。
- 歯の痛みがいつの間にか治まりました。治療は必要ですか?
-
治療が必要かどうか、先ずは歯科医の検査を受けて確認しましょう。虫歯が神経にまで達すると痛みが収まることがあります。この場合、虫歯はかなり悪化しており、直ちに治療が必要です。悩むより検査を受けて確認しましょう。
- 治療した歯がもう一度虫歯になりますか?
-
一度治療しても歯磨きやフロス、歯間ブラシをさぼると被せ物との隙間からや残った歯質に虫歯ができることはあります。毎日の正しい歯磨きなどのセルフケア、定期検診やPMTCなどのプロフェッショナルケアが重要です。
- 歯の神経を取りました。大丈夫でしょうか?
-
歯の神経を取ると歯が折れやすくなったり、変色したりします。また痛みを感じなくなるので、虫歯の再発に気付かず重篤化してしまうというリスクが生じます。正しい治療を受け、定期的に予防処置を行うことで問題は防げます。
- 冷たい水で歯がしみます。虫歯ですか?
-
必ずしも虫歯とは限りません。知覚過敏や歯周病、噛みしめや食いしばりが原因のこともあります。症状が長引く場合は、原因を正しく診断するために、歯科医院の受診をおすすめします。
- 虫歯はどうやって予防すれば良いのですか?
-
基本的にはご自身で毎日の歯磨き方やフロス、歯間ブラシを適切に行うことが最も大事です。歯磨剤もなるべく良いものを使い、洗口液も使用すると良いでしょう。その上で、歯科医院で定期的に口腔衛生指導や歯石除去などの治療を受けることが必要です。
親知らずのよくある質問
- 親知らずを抜歯すると小顔になれる?
-
親知らずを抜く事により目に見えて小顔になることはありません。ただ食欲の減退で少しやせたりその部位に今まで付着していた筋肉が痩せて細く見える可能性があります。
- 親知らずは必ず抜いたほうがいいのか?
-
まっすぐキレイに生えており、対合する親知らずと噛んでいる方、うまっていて生えてこない、押してこない歯の方、虫歯や歯周病になっていない方や、妊娠中や全身疾患で抜歯ができない方、妊娠している方は麻酔が使えないため、抜歯ができません。抜かなくて大丈夫です。ただそれ以外の方は抜歯をお勧めします。
- 抜歯日はいつが良い?
-
当日は運動やサウナ、飲酒などの血行の良くなることは避けていただきたいのでそういったご予定のない日がいいです。腫れのピークは48時間後で元に戻るまでにかかるので10日ほどかかるので、旅行や会議や大事なイベントを避けるのことをお勧めします。
- 一度に何本抜いたら良いの?
-
親知らずは全部で4本あり、4本の親知らずを1日で全て抜歯したいと言う患者さんと1本ずつという患者さんなどいろいろです。ご自分のお口の状況に応じて歯科医師と相談して決めることをお勧めします。
- 親知らずで歯並びが変わる?
-
真横に生えてきた親知らずは手前の歯を押すので前歯の歯並びが段々悪くなり、重なるようになります。
親知らずが原因で歯並びが悪くなっていると気づかないかもしれませんが、結構な割合で親知らずが原因の場合があります。 - 親知らずの抜歯時間は?
-
ケースによりますが 親知らずの抜歯をしている時間は簡単なもので約30分、複雑なもので約60分程度となります。
- 痛い時は抜かないの?
-
炎症を起こして痛い時は、麻酔が効きにくいため抜歯はしません。抗生物質を飲んでいただき、急性症状が落ち着いてから抜歯となります。
- どれぐらいで治るの?
-
骨は3ヶ月から6ヶ月かけて徐々にその穴を埋めて治癒して行きますので、時間がかかります。その間は清潔に保つ必要があります。
- 歯を抜いた後の注意事項は?
-
ガーゼを噛んでもらい30分しっかり噛んでもらい、圧迫止血します。抜いた後3-4時間は麻酔が効いているのでお食事される際はやけど、頬を噛まないように気をつけて下さい。
また激しい運動、飲酒、長風呂、サウナ等血行がよくなることをすると血が止まりにくくなるのでお控えください。歯磨きは抜いた部分以外はしっかり行ってください。
うがいは強くしないようにしてください。抜いた部分で血の塊ができてかさぶたになりますが、それがとれてしまうとドライソケットになり痛みの原因になります。抜いた部分は指や舌で触らないようにしてください。感染して腫れてしまう可能性があります。抗生物質と消炎鎮痛剤を処方しますが抗生物質は毎食後3日分しっかり飲み切るようにしてください。 - 親知らずが痛いです。抜いたほうがよいのでしょうか?
-
腫れを繰り返すようでしたら早めに歯科医院を受診をお願いします。
腫れる原因としては智歯周囲炎が一般的ですのでレントゲン撮影を行い、下の親知らずだと神経と接していないか、上の場合は上顎洞(上顎にある空洞)に近くないかを診査診断を行い当院で抜ける場合は処置いたします。
しかし、痛みがある場合は麻酔が効きづらいため鎮痛剤と抗生物質の投与を行い、症状が落ち着いてから抜歯を行います。 - 痛みはどれくらい続きますか?
-
ケースと個人差はありますが、通常抜歯ですと術後2〜3日は痛みが出ますがほとんど腫れません。埋まっている抜歯ですと痛みと晴れは10日程で治まります。
- 親知らずを抜いた後に歯を持ち帰りたいのですができますか?
-
可能です。
抜いた後に、その場でスタッフや先生にお伝えて頂ければ、抜いた歯を洗浄してお渡しします。
口腔外科のよくある質問
- 口腔外科とはなんですか?
-
顎やお口の中・周りのさまざまな症状に対応する診療項目です。
親知らずの抜歯やインプラント治療、交通事故やスポーツの外傷などの外科的疾患の他にも、口腔粘膜疾患(口内炎や水ぶくれなど)、神経性疾患(顔面神経けいれんなど)などの内科的疾患も対象です。 - 口腔外科では主にどのような疾患を治療するのですか?
-
口腔外科は歯の抜歯、親知らずの抜歯、口腔粘膜疾患、顎関節疾患、顔面骨折、腫瘍の摘出など、口腔および顔面のさまざまな疾患を治療します。
- 口内炎が治りません、病院に行ったほうがいいですか?
-
口内炎のような症状が2週間以上続く、症状がでている箇所の境目がはっきりしない、口内炎よりも痛みが少ない、出血することがある、以上の症状がある場合はご相談ください。
舌癌と口内炎は症状が似ていることもあり、早期に発見することが難しい場合があります。口内炎と思いそのままにしてしまい、気が付いたら進行していることが多くあるのも舌癌の特徴です。 - 親知らずの抜歯はなぜ必要なのですか?
-
親知らずは痛みや歯周炎、歯列不正などを生じることがあるため、抜歯が必要な場合があります。
- 怪我をして歯が抜けてしまいました。どうしたら良いですか?
-
抜けた歯や歯ぐきの状態が良ければ、もう一度再植することが可能な場合があります。
抜けた歯を生理食塩水や牛乳に入れてできるだけ早く歯科医院もしくは病院の歯科口腔外科を受診してください。
抜けてから30分以内であれば処置の成功率が高いと言われていますので、とにかく早めの受診を推奨します。 - 怪我をしてお口の中を切ってしましました。どうしたら良いですか?
-
傷が深く自然に出血が止まらない場合は歯科医院や病院の歯科口腔外科などの医療機関の受診が必要です。
受診までの間は、タオルやガーゼで傷口を圧迫して可能な限り止血を試みてください。 - 歯の移植ができると聞きました。本当ですか?
-
はい、本当です。
保険診療では、虫歯や歯周病などで抜歯した歯の場所に、同一患者さんから抜いた埋伏歯(顎の骨に埋まっている歯)または親知らずを移植することが認められています。
ただし、適用できる条件には限りがあり、また治療の難易度も高いため、必ずしも全ての患者さんで移植がうまくいくわけではありません。
歯の移植を検討する際には、そのメリット・デメリットについて担当医と十分に相談し、リスクを十分に把握したうえで治療に望みましょう。 - お口が乾きやすいです。どんな原因が考えられますか?
-
様々な原因が考えられます。ストレスや高齢化、全身的な病気の治療に用いる薬の副作用や糖尿病、自己免疫疾患、口呼吸、水分不足なども原因の一つです。
治療は生活指導や対症療法が中心ですが、なかなか症状が改善しない場合は歯科医院で診察を受けるのが良いでしょう。 - お口にも癌(がん)ができるって本当ですか?
-
本当です。
口腔がんのできやすい場所は、舌・歯ぐき・頬の粘膜です。口腔がんの発生にかかわる要因は様々ですが、代表的なものは喫煙と飲酒です。不潔な口腔衛生状態、適合の悪い入れ歯などによる機械的刺激なども原因とされています。
異常を感じたら早めに歯科医院や病院の歯科口腔外科を受診しましょう。 - 顎関節症はどのような症状を引き起こすことがありますか?
-
主な症状は顎関節や咀嚼筋の痛み、顎の関節音(「カクッ」「ジャリジャリ」「ミシミシ」といった音)、開口障害(お口を大きく開けづらい、開かない)、頭痛、顔の筋肉の緊張などです。
- 歯の矯正治療を行うにあたり、外科手術が必要と言われました。どうしてですか?
-
歯ならびの不正の原因が顎顔面の骨格にある場合があります。これを「顎変形症(がくへんけいしょう)」といいますが、矯正装置だけでは十分な改善を得ることができません。
そのため、外科手術によって顎の位置や形態そのものの改善を図る治療が必要になります。該当する患者さんが来院された場合、当院では専門の医療機関に紹介させていただきます。
クリーニングのよくある質問
- 歯科医院での歯のクリーニングって何するの?
-
普段の歯磨きで落としきれない汚れである歯石や着色を落とし綺麗にしたり、フッ素の塗布、歯磨き指導といったことを行います。
歯ブラシで落とせる汚れというのは、全体の汚れの約60%程度と言われています。フロスや歯間ブラシを用いたとしても約80%前後と言われています。汚れの放置で歯石となり、自分では落とす事の出来ないものになっていきます。歯石は専用の器具でしか落とすことはできません。また、フッ素は日々の歯磨きで使っている歯磨き粉にも含まれているかとは思いますが歯科医院でしか取り扱えない高濃度のフッ素も塗ってもらうことができます。歯磨き指導では、普段お使いの歯ブラシをお持ちいただき、ご自宅でできるケアのアドバイス等を行っております。 - 歯のクリーニング(歯石除去)は痛い?
-
痛みには個人差がありますが、当院では細い器具を使用しているので痛みを訴える方は少ないです。
またもともとお口の中の環境の良い方は痛みを感じることは少ないでしょう。しかし、歯ぐきが元々腫れている方や歯石が多くたまっている方は、痛みが出ることが多いです。歯石はお水を出しながら超音波振動で除去をしていきます。知覚過敏が強い方は出てくるお水でしみてしまうこともあるかもしれません。 - クリーニングと治療を同じ日に出来ますか?
-
可能です。
治療内容や予約状況によりますのでお問い合わせください。 - 歯のクリーニング(歯石除去)の後は痛い?
-
クリーニングの痛み同様、クリーニング後の痛みにも個人差があります。
たくさん歯石が付いていた方はそれを取った場合、痛みや知覚過敏の症状が出ることがあります。歯石が多くついている方は、歯石により歯ぐきが下がっていることが多く、元々歯ぐきのあった場所に歯石は洋服のような状態で歯についています。それを取ると通常歯ぐきの中にある歯の根が表面に晒されます。神経に刺激が伝わることで痛み等を感じるのですが、歯ぐきの中にあった歯の根の部分はエナメル質がなく、象牙質がむき出しになっています。その象牙質が晒されているということは、神経へ刺激が伝わりやすくなっているため、歯石除去後に知覚過敏の症状や痛みを感じる方がいます。 - 歯石と歯垢(プラーク)は違うの?
-
歯石は歯垢(プラーク)が固まったもの、歯垢(プラーク)は細菌の塊です。歯石はザラザラしているため表面に歯垢(プラーク)が溜まりやすく、歯周病が発症しやすくなります。歯石は歯ブラシでは除去できないため、歯科医院を受診し除去してもらいましょう。歯垢は、放置していると虫歯や歯周病の原因になるため注意が必要ですが、歯磨きやフロス、歯間ブラシによって取り除くことができます。
- 歯石取りで血だらけになるのはなぜ?
-
歯ぐきに炎症があるため出血します。炎症が起きているということは歯垢や歯石が溜まっているということで出していい血です。歯石が溜まっている場合、歯石取りで出血する方は多いです。歯石取りが終わると自然に出血が止まります。
- 歯石を除去したら歯がしみるのはなぜ?
-
歯石を除去することで、歯の根元が露出し、刺激が神経に伝わることでしみやすくなります。数日間しみる状態が続くこともありますが、徐々に落ち着きます。
症状が落ち着かない方はご相談ください。 - 歯石はどのくらいの頻度でとればいいですか?
-
歯石の除去は、一般的に3ヶ月~半年くらいのペースで行います。
しかし、お口の状態や歯石の量で通院していただく頻度は異なるため、歯科医師または歯科衛生士の指示に従いましょう。 - 歯石取りの費用はいくらですか?
-
歯周病治療の一環として保険が適用されます。
保険診療で検査代を含めて4,000円前後が相場です。
歯ぎしりのよくある質問
- 寝ているときの歯ぎしり防止にマウスピースは作れますか?
-
はい。
歯ぎしり、食いしばりのためのマウスピースは保険適用3割負担で約5,000円ほどで作成できます。 - 歯ぎしりは治りますか?
-
残念ながら歯ぎしりは治りません。
歯ぎしりの原因は睡眠時の脳の反応だといわれており、深い眠り(ノンレム睡眠)から浅い眠り(レム睡眠)へ移行するときに現れます。そのため治すことは難しいですが、ナイトガードのような夜装着して寝るマウスピースで歯を保護したり、ボトックス注射で咬筋にアプローチしてそもそもの咬む力を小さくするといった事を治療としています。 - 歯ぎしりと歯周病と関連はありますか?
-
歯周病に罹患してる場合、歯周組織(歯根膜や歯槽骨)へダメージを与え、歯周病を促進してしまう可能性があります。
- 歯ぎしりとは何ですか?
-
歯ぎしりとは強い力で、上下の歯と歯をかみ合わせ前後に動かすことです。原因は睡眠時の脳の反応だといわれており、深い眠り(ノンレム睡眠)から浅い眠り(レム睡眠)へ移行するときに現れます。
ストレスで強くなってしまうので、歯を守るためにも対策が必要です。 - 歯ぎしりの原因は何ですか?
-
歯ぎしりの原因は睡眠時の脳の反応です。ストレスで強くなります。
- 歯ぎしりをするとどうなりますか?
-
歯が削れ、欠けてしまうことがあります。歯ぎしりによって歯に掛かる力が強くなり、毎日のように続いてしまうと歯が欠け、擦り減っしまいます。
また、顎にも負担がかかり顎関節がズレたり変化することで顎関節症が生じることがあります。顎関節症は顎の痛みや口を開けづらくなること、顎を動かすと音が鳴ることなどが主な兆候です。硬い食べ物や大きな食べ物が食べづらくなることがあります。 - 飲酒や喫煙は歯ぎしりと関係がありますか?
-
明確なメカニズムは分かっていませんが、飲酒や喫煙習慣のある方に起こりやすと言われています。
口臭のよくある質問
- 虫歯でもない、歯周病でもないのに口臭が気になります。
-
口臭は以下の4つの分類に分けられます。
- 生理的口臭・・・空腹時や、口の中の細菌が増殖して発生する口臭です。健康な人でも起きます。
- 病的口臭・・・歯周病、大きな虫歯など、口腔内由来のものと、内臓の病気など全身由来のもので発生します。
- 外因性口臭・・・お酒やタバコ、臭いのある食べ物によるものです。
- 心因性口臭・・・口臭がないにも関わらず、本人の思い込みによる口臭です。
「お口の中が乾いている」「舌苔がある」などの原因の場合、お口をゆすいで潤すことや舌ブラシで清掃するなどして改善できます。
お口のなかを潤してもすぐに口臭がでてしまう場合は、虫歯や歯周病などお口トラブルが原因となっている可能性が高いため、その問題を解決しなければ止めることはできません。 - 口臭をなくす方法を教えてください。
-
口臭の原因は全身的なものを含め様々ですが、口臭予防の基本は歯磨きと舌磨きです。舌の上の白い汚れは舌苔と呼ばれるものです。
舌には角質が多くありますが、その角質が伸びて硬くなるとその隙間に細菌がたまります。舌苔は舌を磨くことで除去することができますが、無理やり除去すると舌を傷つけてしまう可能性もあります。舌磨きは大切ですが、舌苔を取るだけを考えて磨きすぎないように注意してください。
他にもうがい薬を使用することは口臭予防には効果的です。 - 口臭で悩んでいるのですが治療できますか?
-
口臭が気になる場合には、口内で発生源になっている箇所があるか確認できます。口臭の原因の多くは、歯石や口内に残留した食べカス汚れとそこに繁殖した細菌です。不適合の補綴物や、良くない歯並びがあると、汚れが溜まりやすいので要注意です。むし歯や歯周病を放置すると細菌が繁殖して口臭につながるので、治療して定期的なクリーニングで良い状態をキープしましょう。
口内以外が原因の口臭が考えられる場合には、他科の受診をアドバイスいたします。 - 口臭が気になります。どのような治療法ができますか?
-
お口の中の病気が口臭の原因だった場合は、しっかりとした歯周病や補綴の治療が必要だったり、正しい歯ブラシの当て方、ケアのタイミング、ケアの仕方などを詳しくお伝えいたします。
知覚過敏のよくある質問
- 知覚過敏とはなんですか?
-
知覚過敏とは、歯の知覚が過敏になって歯がしみる状態です。
表面のエナメル質の中に象牙質、その中に神経という組織があり、神経に刺激が伝わることで我々は痛みを感じます。
何らかの原因でその象牙質が露出することで、冷たいものや歯ブラシの刺激などが神経へ伝わってしまい、一過性の痛みを感じることをいいます。 - 歯ブラシの力が強いと知覚過敏になりますか?
-
なります。
ブラッシングの力が強いと歯茎が下がってセメント質という根っこの部分が露出したり、歯が摩耗して象牙質が露出してしまい、知覚過敏が起きてしまいます。
歯ブラシの使い方、力の入れ具合など一緒に練習しましょう。 - 虫歯ではないと言われたのに、歯ブラシなどで歯がしみます。
-
歯ブラシをしているときや冷たいものを飲んでいるとき、歯の神経に触れるようなズキっとした一時的な痛みは知覚過敏の可能性が高いです。加齢や歯ぎしりで歯茎が下がっていたり、強すぎる歯磨きや電動歯ブラシが原因です。確実な予防方法はありませんが、虫歯なのか自分では判断しにくいと思いますので早めに受診することをおすすめします。
- 知覚過敏は治りますか?
-
薬や知覚過敏用の歯磨き粉などはありますが、基本的には完治させるというより上手く付き合っていくような形になります。
あまりにも大きく削れている場合はレジンというプラスチックをつめて修復したりします。